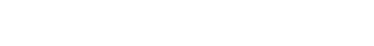Q.やり遂げてきた仕事について教えてください
A.【1年目~】技術開発本部から工場出向へ――両方の仕事を知る意義とは
1-2年目は、技術開発部でアイスの実の試作機の電気設計を担当しました。1年目から一担当者として扱われ、試作機のレベルであれば、1人で任せてもらっていました。勿論わからないことがあれば先輩や上司が教えてくれますし、サポート体制はありますが、若手のうちから色々なことにチャレンジさせてくれる会社だなと思った記憶があります。
3年目からは、佐賀にある乳製品を作っている工場に出向し、現場保全、新規ラインの導入、ユーティリティ設備管理を担当していました。工場で働く経験を通じて、工場でラインを稼働させてくださる方々の苦労や思いを深く知ることができました。技術開発部の仕事において、現場のリアルを知ることは大きな強みになります。自分が開発した機械を導入する際、事前にいくらシミュレーションをしていても、実際に導入すると想定外の不具合が出てきます。現場のリアルを知っていると、その不具合を事前にある程度予測できるだけでなく、導入後に発生した不具合に対するリカバリー策を現場の従業員の方と検討する際、より建設的な話をすることができます。
工場は小さな町のようなものです。実際に製品が流れる装置のほか、電気、ガス、排水処理等のインフラが、どういう原理で作られて、処理されて、届けられているのか。国で定められている排出基準や、それを守るためにどうすればいいのか。原理原則を学ぶことができました。この時の経験が、現在の業務にも大きく役立っています。
【5年目~】SCMのDX担当に――各分野のプロフェッショナルと一緒に新しいものを創り出す
5年目からは、生産性・品質向上、業務効率化、競争力向上を目的に、サプライチェーン全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進を行う部署に所属しています。私自身は、国内外の新工場の立ち上げ時のデジタル技術導入を主に担当しています。具体的には、建物の情報インフラ設計、入退室管理や監視カメラなどのセキュリティ、AGV(自動搬送車)や生産設備の情報連携、AIやVRなどの最新技術の開発・導入まで、幅広く手掛けています。
工場を一から立ち上げる際、予想もしていないトラブルはつきものです。原因を究明するために装置からのデータを分析をしたり、実際の動きやオペレーターの操作を観察したりと、工場の現場で作業をすることもあります。最新技術や分析手法をピックアップ、習得しシステム開発しながら現場に出て作業するのはとてもハードですが、製造現場から感謝されるのがとても嬉しく感じています。
ちなみに、新しい工場を立ち上げる際は、建築や各工程のプロフェッショナルがいくつかのチームとなって計画の立案、実行を行います。その中で、私たちデジタル担当者は、すべての担当者と連携をとる必要があります。プロフェッショナルな方々と肩を並べながら、様々な分野から多くの事を学べるので充実感を得ながら仕事ができています。
【10年目~】10年経っても日々新しい挑戦が待っている環境!
2024年6月に出荷を開始した新しい粉ミルク工場では、工場全体を集中管理するマニファクチャリングコントロールセンター(MCC)を構築し、省人化された工場でも安心・安全で高品質な製品を製造するスマートファクトリーを実現しました。
最新のデジタル技術とグリコのノウハウを集約したスマートファクトリーを実現しましたが、常に最新のスマートファクトリーであり続けるために、環境に配慮した生産を推進し、最小限の電力やガスで生産できるエネルギーマネジメントシステムの構築にも挑戦しています。

Q.
どんな学生でしたか?
A.
ものづくりへの熱い情熱
小さい頃から新しいもの好きで、 学生時代には自作でPCを組んでみたり、マイクロコンピュータでドローンもどきを作ったりと、とにかく手を動かしてモノを作り上げることが大好きでした。そんな中で、高専時代に受けた、仮想の工場の模擬ラインのプログラムを1から作る授業がとても楽しかったことから、将来も開発の仕事がしたいという思いがずっとありました。地元である大阪に本社があるということと、消費者として親しみがある(小学生の時にグリコピア見学に行き、とても楽しかった思い出がありました(笑))という理由から、Glicoを受けました。Glicoの採用面接では、入社後にやりたいことや志望理由を正直に話して内定をもらい、等身大の自分が評価された、と嬉しかったことを覚えています。
人に頼られるのが好きで、学生の頃は学生会の執行部で会長になり、率先して物事を進めることを多く経験しました。Glicoでは、新人の頃から主担当やリーダーなどを任され、その後もどんどん裁量権が大きくなるため、学生のころにリーダー経験を積んでいてよかったなと感じています。現在、入社10年目。様々なプロジェクトに携わる担当者としてカバーする範囲がとても広くプレッシャーを感じることもある一方、自由度が大きく自身で考えゼロから形にしていく楽しみがあります。
これからも新しい技術を駆使して、新しいものを創り上げます!
Glicoでは、世界初や業界初の挑戦を応援してくれるので最近はARやメタバース技術を用いて工場を仮想空間に拡張させる取り組みを新たに挑戦しています。今後も、お客様に安心・安全で高品質な製品を届けるだけでなく、地球環境や工場で働く従業員にも優しい工場を、デジタル技術を駆使して創り上げていきます!
9:00出勤・メールチェック
10:00新工場の稼働データ分析
11:00更なるデータ活用に向けて工場メンバーとディスカッション
12:00食堂で昼食
13:00エネルギー監視システムの構築検討
16:00海外のAIベンチャーと商談
17:00メールチェック
17:30退社
19:00趣味でAWSを使った自宅のIoTシステムの構築

Q.
あなたにとって「Glico×エンジニア職で働く」とは?
A.
高い専門性と豊富なノウハウを持つ同僚と切磋琢磨できる環境
Glicoのエンジニア部門には、高い専門性と豊富なノウハウは勿論のこと、創意工夫の精神を持った先輩方が多く在籍しており、それらを吸収しスキルとして発揮できる場が整っています。世間の一般常識から考えると思いもよらないような機械の使い方を知っている先輩が沢山いて、新人の頃は、その引き出しの多さにびっくりしていました。それは、「普通ならできないけれど、こういう工夫をすればやりたいことが実現できるのではないか」「やってみよう」という、創業当時から創意工夫の精神が受け継がれているのだなと感じます。
技術開発部のアットホームな雰囲気と、同僚・上司部下間の仲の良さも、大きな魅力の一つです!