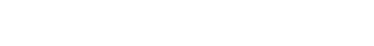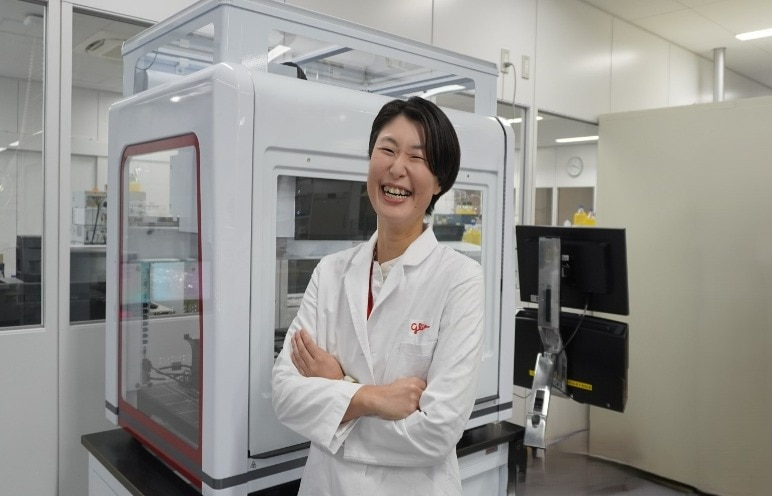Q.やり遂げてきた仕事について教えてください
A.経験のない研究分野への挑戦――研究者としての礎作り
博士課程卒業後、グリコグループのグリコ栄養食品株式会社に入社し、半年間食品原料の開発に携わりました。その後、江崎グリコの基礎研究部門(当時の健康科学研究所)に出向し、腸内細菌に関する基礎研究に従事しました。腸内細菌の研究分野には馴染みがなく、出向直後はかなり戸惑いましたが、先輩や上司、共同研究先の先生方に一から指導を頂き、次世代シーケンサーを使った腸内細菌叢解析や機械学習での予測モデルの構築等に取り組みました。自分にとって未知のことに取り組むのは大変でしたが、知識が身についてくるにつれて周りとディスカッションできるようになるのが嬉しく、研究者としての成長ややりがいを感じました。
入社5年目の頃から、研究テーマリーダーとして研究テーマの推進を任されるようになりました。研究の企画をして、予算を取ったり、スケジュール管理や同じ研究テーマを担当するメンバーへの業務割り振りをしたりします。これまでの立場とは違い、研究テーマの推進をマネジメントする側の難しさを感じています。研究は仮説と計画を立てて進めるものですが、なかなか思った通りにはいきませんし、企業として研究をスピーディーに事業に生かすことも求められるため、難しさはあります。その一方で、自分で考えて研究を進めていくやりがいは大きいと感じています。実際に、自分が担当した研究テーマで、エビデンスを強化するために社内ではできない実験の必要性を訴え、共同研究を提案し実現できたのは、テーマリーダーとしての一つの成果だと思っています。研究業務以外では、研究員のスキル向上や、研究所全体でより質の高い研究活動ができるように、新入社員のOJTや、勉強会の主催、機能性表示食品関連の業務などを行っています。
これからもお客様にグリコの商品が愛されるよう、研究の側面からしっかりとしたエビデンスと価値を創出していきたいです!
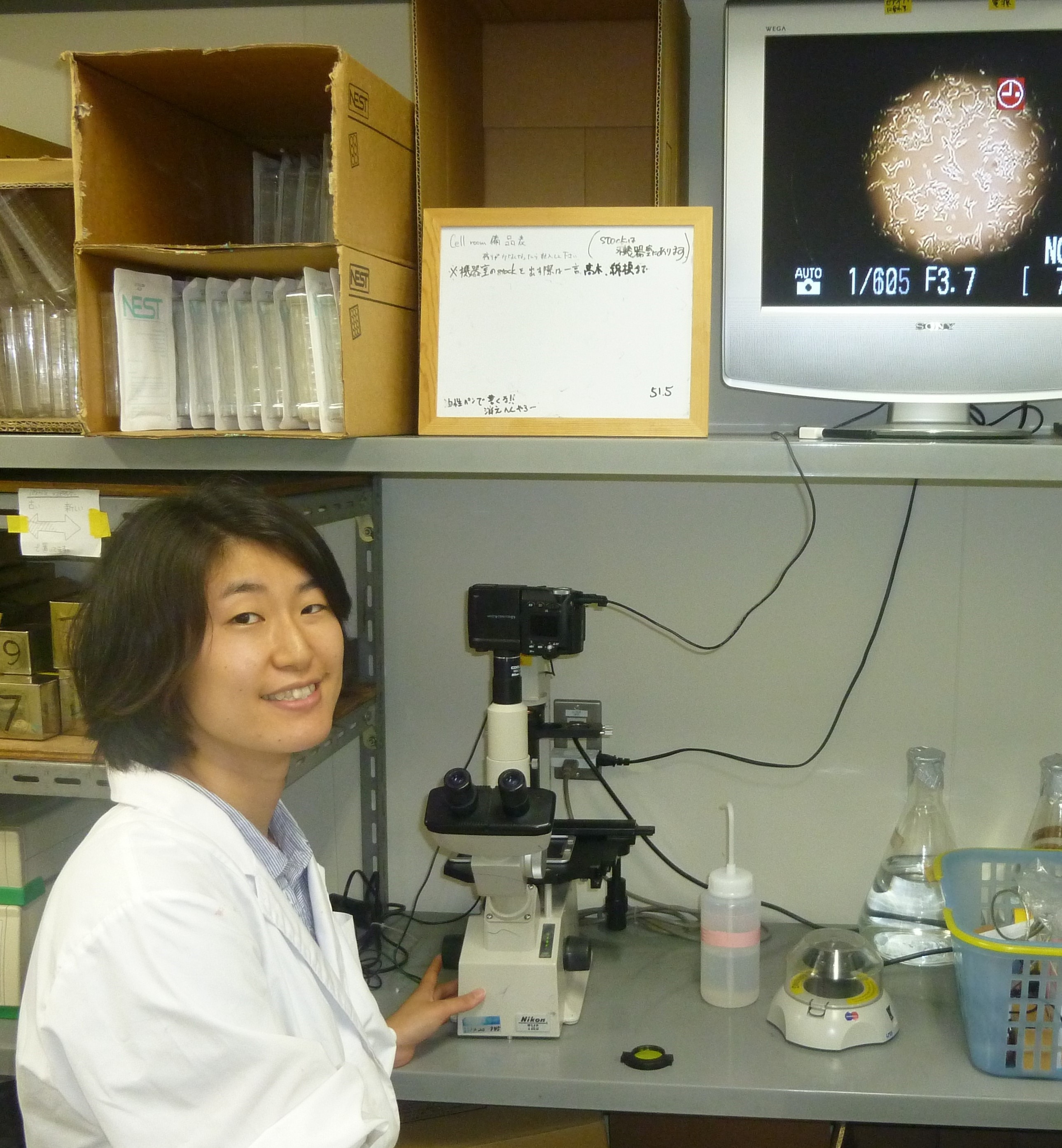
Q.
どんな学生でしたか?
A.
今の自分の基礎を築いた学生時代――「興味」と「基礎力」
中学・高校生のころから生物の授業が好きで、特に人体の構造や臓器・器官の働きなど(平たく言えば、“人間が生きている仕組み”)に興味を持っていました。大学で生化学や栄養学を学び、ヒトが健康に生きるためには「食」が大事だと感じて、大学院では食品や栄養素の機能性を研究している研究室に入りました。博士課程在学中には、日本学術振興会の特別研究員に採用され、自分の研究テーマの将来性や実現可能性をアピールして研究助成金を獲得する経験もしました。
自分が書いた申請書や論文が先輩や指導教官によって真っ赤に添削されて返ってくる度に、めげずに修正しては提出する、を繰り返していました。今振り返るとこういった経験が、目的達成のために必要なステップ(計画)を論理的に構築する力を鍛えてくれたのだと思います。
研究者としての社会的責任を果たすことの重要性
研究者としてのアウトリーチ活動にも興味があり、課外活動では、小中学生対象の科学実験教室や高校生の進路相談会なども行いました。 これらの活動を通じて、自分を客観視し相手の立場になって分かりやすく伝えることの重要性や、“研究者”という立場が与える他者に対する影響力・責任の大きさを強く意識するようになりました。
Glicoに入社後も、会社員とはいえ研究に携わっている人間であることは変わりません。より質の高い研究活動ができるように、高い倫理観とリーダーシップを発揮して、ヒトが健康に生きるために重要な「食」の分野で貢献していきたいです。
9:00出社、メールチェック等
9:30実験
12:00昼休み(昼食後にテニス)
13:00社内のプログラミング勉強会に参加
14:30実験データのまとめと解析
15:00共同研究に関する定期打合せ
16:30チームメンバーと進捗共有
17:45実験室の終業点検(当番制)
18:00退勤
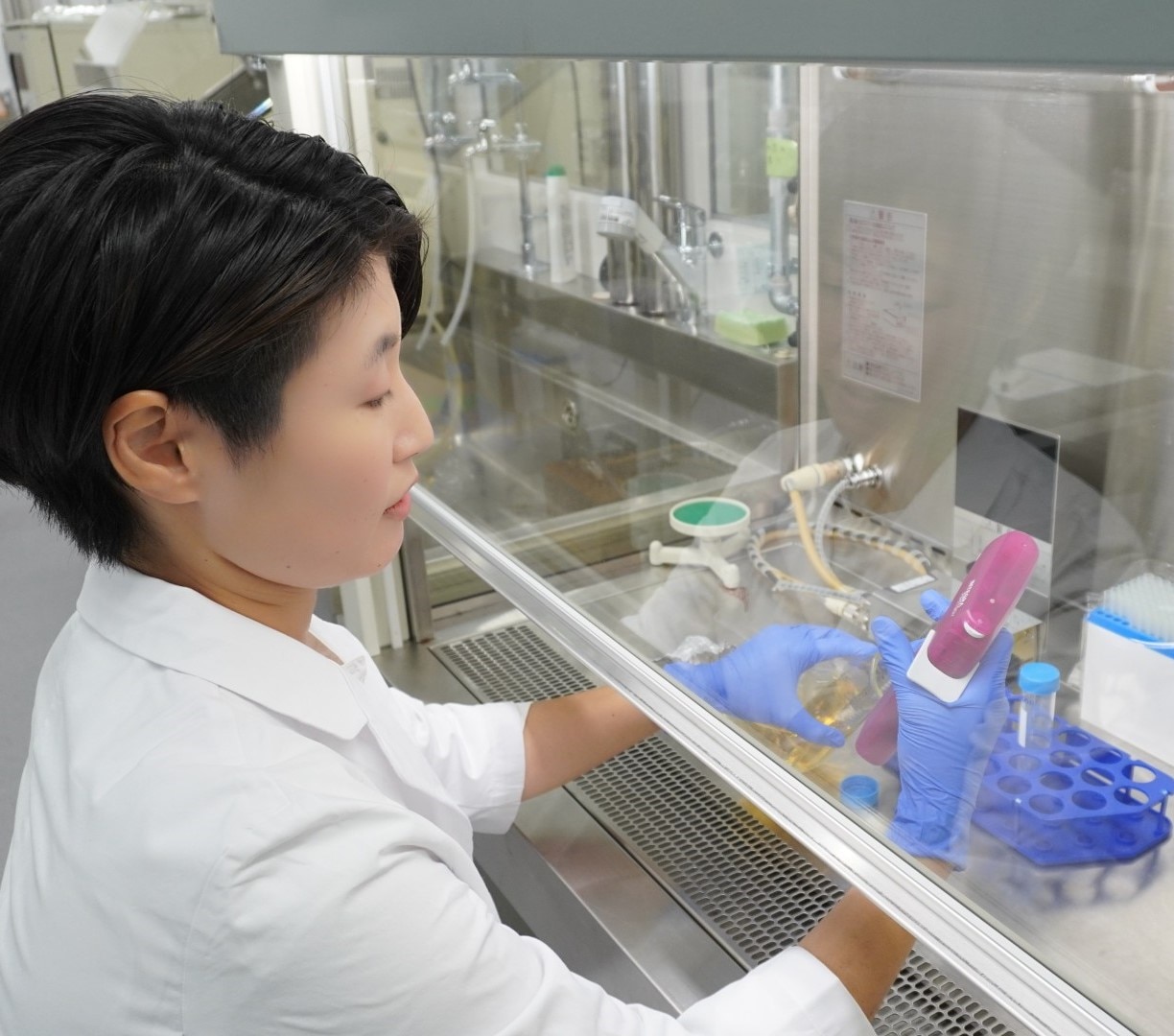
Q.
あなたにとって「Glico×基礎応用研究職で働く」とは?
A.
尊敬できる仲間と一緒に――「研鑽」と「挑戦」が両立できる!
Glicoの基礎応用研究職では、高度な研究経験やスキルを持つ人材が活躍しています。また、相談に乗ってくれるメンバーがたくさんいて、お互いのスキルや研究の質を高めていく風土があると思います。自分の専門分野を深めつつ、新しい挑戦を恐れず楽しむことができる方にとって、非常に魅力的な環境です。ぜひ、私たちと一緒に研究を通じて社会に貢献しませんか?